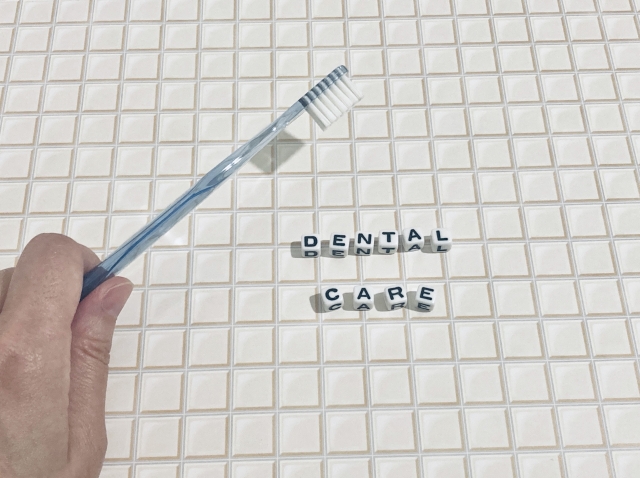歯科コラム
-
歯の汚れ、それはステイン

食品の中のポリフェノールが原因
1月は新年会などイベントも多く、公私ともに多忙になる方も多いと思いますが、口腔ケアも忘れずにしっかりしておきましょう。改めてご自身の歯をご覧になって歯のくすみや汚れが気になるという方もいらっしゃるかもしれません。この歯のくすみは歯の表面についた着色汚れで、“ステイン”と呼ばれていますが、その原因は食品に含まれる色素によるものと、喫煙や漢方薬やうがい薬の色素などがあります。
歯の表面はペリクルといって唾液タンパク質の膜ができて歯を守る一方、このペリクルには色素を吸着する性質があるため着色汚れとなってしまうのです。喫煙による歯の黄ばみも同様でタバコに含まれるタールがペリクルと結びついて着色します。タールはもともと黒色なので歯も黒っぽくなってしまうのです。
ステインになりやすい食品の代表例として赤ワインやコーヒー等がありますが、これらの食品に含まれる色素はポリフェノールといって、植物が紫外線や乾燥、害虫や菌など外的な刺激から身を守るために作り出す色素や苦味・渋み成分です。ポリフェノールは8,000種類以上あるといわれており、色素の濃いものとして赤ワインのアントシアニンのほか、緑茶のカテキン、コーヒーのクロロゲン酸類、カカオに含まれるエピカテキン、カレーのスパイスに使われるウコンのクルクミンなどがあげられます。お茶に多く含まれるタンニンの場合はカルシウムや鉄のような金属イオンやタンパク質などと結びつきやすいので、食品中の色素や有機物を歯の表面に沈着させ、これもまた歯の着色汚れの原因の一つとなります。着色汚れになりやすい赤ワイン、コーヒー
飲み物に含まれるポリフェノールの量(1杯100mlとして換算)を比べると多い順に赤ワイン230mg、コーヒー200mg、緑茶115mg、ココア62mgとなり、とくにワインとコーヒーに含まれるポリフェノールの量が多く、歯に色が着きやすいことも納得できます。
日々積み重なった着色汚れは歯ブラシでもなかなか落ちません。ですから、ごしごしと強く歯を磨いても汚れが落ちないばかりか逆に歯の表面を傷つけ、その小さい傷から着色汚れが染みてより色素が沈着してしまうことにもなりかねません。
ステイン予防のためには普段からこまめに歯ブラシをすることと、その際は大きな力を加えず歯ブラシが軽く接触している感覚で磨くことが大切です。歯科衛生士によるクリーニングで落とすことができますので歯科クリニックに定期的に受診されることをお薦めします。
-
歯を失う原因の第3位は?

神経を取ると歯の寿命が短くなる
むし歯が歯の奥まで進んでしまい、神経を除去した歯がある方は多いと思いますが、神経を抜いた歯は見た目変わらないように見えて、長い目でみるとやはり違ってくるといえます。
神経を取る治療は根管治療(歯内療法)といって、歯の真ん中を通る神経まで炎症が達してしまった場合に細菌に感染している神経をきれいに取り除いて洗浄・消毒・薬剤充填を行う治療のことです。
歯の神経は専門用語で「歯髄(しずい)」といいますが、歯髄にはたくさんの血管も含んでいて歯の健康に重要な役割を果たしています。その歯髄を除去してしまうと歯に栄養を届けられなくなるので歯質がどうしてももろくなってしまうのです。そのほかに痛みを感じないため、気づかないうちに虫歯が重度にまで進行してしまうといった弊害もあります。
歯がもろくなってしまうためひびが入ったり割れやすくなるというリスクも高まり、歯髄のある歯に比べると奥歯で7.4倍、前歯で1.8倍にもなるという報告もあります。歯髄を除去して歯に血が通わなくなるため、歯の寿命も約10年近く短くなるともいわれています。
歯根の破折を防ぐ方法としては、被せ物をする際の土台をファイバーコアという弾性のある素材にすることなどが推奨されています。金属製のメタルコアは強度が強いため歯根に大きな負担がかかり、くさびを打ち込むように歯根を割ってしまうことがあるためです。接着して保存する治療法も
歯が破折した際の治療法というのは現状では確立しておらず、抜歯するのが一般的です。歯科大学においても歯根破折科はありません。ただ、ひび割れた歯の隙間に歯科用接着剤を流し込んで接着して保存する方法が試みられていて、成功例が増えてきています。
日本人が歯を失うリスクはむし歯と歯周病が2大原因ですが、続く第3位が歯根の破折で17.8%を占めています。今後、むし歯と歯周病の罹患者が減っていけば、「歯の破折」が歯を失う原因の1位になる可能性も十分にあり得るとされており、治療法の確立がいそがれるところです。
神経を抜いた歯については破折のリスクを抱えているということを念頭において、日常の口腔ケアはもちろん、むし歯の再発防止も含めて定期的な歯科検診とクリーニングを受けて長持ちさせたいものです。
-
オーラルケアが健康寿命を伸ばすことへの理解度は日本が第一位

世界15カ国での口腔衛生意識調査から
11月8日は「いい歯の日」として知られていますが、平成5年に日本歯科医師会が「8020運動」推進しようとアピールしたのが始まりです。この日にちなんで世界の各国の口腔衛生への意識や行動について、サンスターが行った調査から見ていきたいと思います。この調査はヨーロッパ、アジア、南北アメリカ地域の15カ国の18歳から65歳までの男女15,000人を対象に2021年4月に行われました。
普段のオーラルケアについては、第一位が「1日2回歯を磨く」が15カ国平均で53%と最も高く、日本も56%と同レベルですが、「舌を磨く」、「フッ素入り歯磨きで磨く」、「年に2回歯科医院に行く」、「食後の歯磨き」、「フロスの使用」、「電動歯ブラシの使用」、「砂糖入りのお菓子や飲み物を避ける」という項目で、各国平均を下回っていることがわかりました。とくに「洗口液を2日に1度以上使用する」日本人の割合は21%と各国平均の33%を大きく下回り、口腔ケアは歯磨き中心であることがうかがえます。
お口の悩みとしては最も多い回答は知覚過敏(各国平均30%)で、二位「むし歯がある」、三位「歯ぐきに炎症がある、歯周病がある」と続きます。知覚過敏について日本は19%と低く、最も多いお悩みは「口臭がある」(34%)で、15カ国の中でもトップでした。ちなみに口臭を気にするエリアはアジア地域で高い傾向にあり、最も少ないのはブラジルでわずか8%でした。甘い物の誘惑は各国共通
日本人の回答で注目すべきは、「口腔内の健康が身体全体の健康に関係することを理解している(健康寿命の延伸)」人の割合が38%と、各国平均の21%を大きく上回ってトップだったことです。オーラルケアが全身の健康、ひいては健康寿命を伸ばすことが周知徹底されてきている成果であり、口腔衛生への理解度が高まっていることがわかります。
また、魅力的な笑顔づくりのために希望する施術としてホワイトニングが48%と日本も含めた多くの国で人気で、矯正治療(16%)、インプラント(11%)等を上回っていました。
ちなみにお口の健康のためにやめたいと思っている習慣のトップ3は甘いお菓子(中国がトップで31%)、喫煙(ドイツとスペインで最も高い)、歯に着色しやすい飲み物(イタリア、インドネシア、ブラジルで高い)という結果で、やはり甘い物の誘惑は各国共通のようです。
この調査で各国の文化や習慣の違いもありますが全体的にはオーラルケアへの関心が高く、日頃からお口の健康に気をつかっていることがわかります。
-
甘い物が止められない理由

依存症に共通する脳の回路
むし歯になりやすい食べ物の一つとして甘い物があげられますが、この甘い物を食べ始めると止まらない、ついつい食べ過ぎてしまうという方が少なくないかもしれません。甘い物はなぜやめられないのか、最近その理由が解明されて話題を呼んでいます。
チョコレートやクッキー、ケーキ等は砂糖や油脂が多く含まれる高カロリーな食品を食べると私たちは美味しい、うれしい、幸福だと感じて脳内にはドーパミンという神経伝達物質が放出されます。脳はこの「幸福感」を覚えていて、また同じ快感が得られるような行動を繰り返すようになります。食べることで幸せを感じて、また食べたいと思う回路(脳の報酬系回路といいます)があるからこそ、人類はここまで生き続けて来られたといえますが、飽食の時代といわれる現在においては、このシステムは肥満を促すシステムとして作用するようになってしまったといえます。
また、病的に肥満している人の脳はドーパミンを受け取る受容体の数が少なくなっていて、食べ物に対する反応が鈍くなっているといわれています。つまり、「食による快感」が得られにくいため、より美味しいものを、より大量に食べることで満足感を得ようとするのです。そのためにさらなる肥満を招くという悪循環に陥っているといえますが、ドーパミン受容体の減少は薬物依存症の人の脳でも認められていて、「食べ過ぎを止められない」という症状は薬物依存症と似ているということがわかってきました。ただ、甘いものや高脂肪の食べ物がドーパミンの受容体数を減少させる理由についてはまだ、よく分かっていません。スイーツを甘くみてはいけない
甘いお菓子やジャンクフード等はついつい口に入れてしまいがちですが、依存性に陥る可能性があるので甘く見てはいけないということがわかります。甘いものの取り過ぎは歯の健康にも悪影響があり、とくに間食はむし歯のリスクを高めます。食事のときには口の中が酸性に傾くため、歯の表面のエナメル質からカルシウムやリンが溶け出しますが、食後は唾液の作用によって中和され、唾液に含まれるカルシウムイオンとリン酸イオンによって、歯の表面が修復されますが、頻繁に間食を取ると、この修復が間に合わなくなり、むし歯へと進行する恐れが出てくるためです。
食後、歯を磨いたらそれ以降はなにも口に入れないことがベストですが、間食は1日に1回など回数を決めるだけでも、むし歯予防なりますのでぜひ実践してください。
-
資産価値を目減りさせないために

歯一本のお値段は?
金融の記事のようなタイトルですが、もし仮に一本の歯に資産価値をつけるとしたらどれくらいになるか、考えてみようというのが今回のテーマです。
交通事故で歯を失ってしまった場合の賠償請求額は一本80万から120万円という判例があります。歯の本数は親知らずを除くと28本になるので、合計すると2,240万〜3,360万円ということになります。お口の中に家が買えるほどの資産があると聞くとびっくりしますが、一般財団法人日本予防医学協会では“歯一本の価値について”各方面に聞いて調べています。歯科医師からは一本104万円という回答が得られ、この中には噛み合わせや歯並びを揃える費用等も含まれているそうです。お口の中全体では28本分で2,912万円と、前述した賠償請求額に近いものになります。
「いやいや、歯の資産価値はそんな安いものではないよ」というのがアメリカの一般的な人の回答で、歯一本は500万円の価値があるとしています。28本では1億4,000万円とかなりの高額です。
一方、気になる日本人の回答ですが、歯一本は約35万とかなり低い額となっています。この差はどこから来るのか興味深いところですが、健康保険制度によって治療費の負担が原則3割で済む日本に比べて、全額自己負担のアメリカでは気軽に治療は受けられないという背景があるのかもしれません。実際の歯の治療費も日本の5~10倍と跳ね上がるので歯そのものの価値もより高いものと認識されるのかもしれません。実際に虫歯の治療に20~30万円とかかるそうなので、できるだけ歯科医院の御世話にならないよう口腔ケアには熱心にならざるを得ないということに納得がいきます。その結果、治療から予防へという意識の転換が自然となされていることがわかります。予防に軸足をおいて
日本の場合は国民皆保険制度によっていつでも手軽に治療が受けられるという安心感からか、予防重視へと舵が切れないでいるのが現状かもしれません。
歯という資産は日頃のメンテナンスが悪いとその価値が目減りしていき、最悪の場合は資産ゼロにもなりかねません。ただ、この資産を維持することは難しいことではなく、地道なホームケアと定期的なプロのケア(歯科クリニックでの定期検診とメンテナンス)の両輪で進めていけばよいのです。むし歯や歯周病が重症化して治療するよりも、よほど経済的にも身体的にも負担がかかりません。
いずれにしろ、歯は私たちの健康を支えるうえで大切な役割を果たしており、一度失うとお金では取り戻すことはできないかけがえのない存在です。症状が出てから治療するのではなく、とくに問題がないときにこそ予防に取り組むという発想の転換が大切だといえます。
医院案内
治療案内
24時間受付メールで診察予約
電話にて診察予約